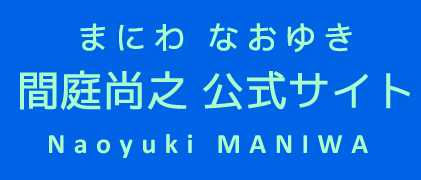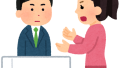近年、福祉分野においても「経営感覚」、「効率化」、「イノベーション」といった言葉が盛んに用いられています。厚労省も「介護分野における生産性向上」とか言ってます。いわゆる「意識高い系」です。福祉事業でビジネス的に意識の高い議論が交わされること自体は、否定されるものではありません。むしろ好ましいことです。しかし、社会保障の基盤となるべき「人権意識」が薄弱で、ビジネス面ばかりが強調されてしまえば、本質的な福祉の実現には、つながらないのではないでしょうか。
以前、私が参加した高齢者福祉のシンポジウムで、そのことを痛感する出来事がありました。福祉に通じているはずの司会者が、「自分の妻をどんな老人ホームに入れればいいでしょうか」と発言したのです。その場にいたシンポジスト(施設経営者など)は、入所費用や施設の設備、運営形態といった「経済的合理性」の観点から答えを出そうとしていました。しかし、本来であれば「妻がどう生きたいのか」、「どのような支援を望んでいるのか」をまず問うことが、福祉に携わる者として当然の姿勢であるはずです。
ソーシャルワークの倫理は「利用者の意思を第一に尊重すること」にあります。これは単なる理念ではなく、支援の現場での行動規範であり、支援の出発点です。その原則が置き去りにされ、経済的な検討だけが優先される場面があまりに多いのが現実です。シンポジウムの光景は、その象徴のように思えました。私は暗澹たる気分にならざるを得ませんでした。いくらビジネスパーソンとして意識高く振る舞い、経営指標や効率性を語っても、「当事者の意思」を軽視したままでは良き支援は、決して実現できません。強調したいのが「当事者の意思」という点です。家族の意思ではありません。
障害者権利条約のスローガンは、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」です。この理念は、少なくとも心ある福祉現場では徹底されています。私たちは、もっとも不利益を被りやすい当事者の意思を第一に尊重して支援をしなければならないのです。それが福祉分野で浸透している「人権」なのです。
福祉的支援とは、当事者の生活と尊厳に直接関わる営みです。経済的合理性を語ること自体が悪いのではなく、当事者を中心に据えたうえでなければ、人権を損なった支援になってしまうことを言いたいのです。
実際にこのような意識の欠如は、現場に深刻な弊害をもたらしています。利用者本人の意思確認をなおざりにしたままサービス利用が決定されること、家族や施設の都合が優先されて本人が望まぬ暮らしを強いられること。そこには「効率化」、「持続可能性」といった耳障りのよい言葉が並んでいても、当事者の人生は置き去りにされてしまいます。
福祉労働に人権意識が伴わなければ、いくら制度や事業の枠組みを整えても、本質を欠いた空洞の支援しか残りません。
求められているのは、単なるビジネス的発想ではなく、「一人ひとりの生き方をどう尊重するか」という根本的な問いに立ち返る姿勢です。その視点なくして、福祉の未来は語れないと強く感じます。ビジネス的に意識高い系、大いにけっこうです。しかし、当事者を中心に据える人権意識がなければ、支援の体裁をなさないのです。