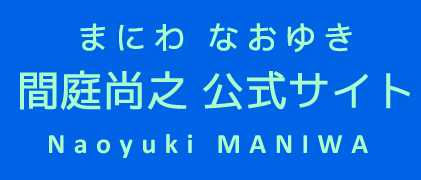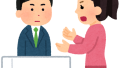2025年5月中旬、ある成年後見人がたいへんな困難に陥ってしまいました。その成年後見人は、墨田区に事務所をかまえる司法書士のXさんです。東京の東部地区で何人もの高齢者や障がい者の成年後見を担い、地域からの信頼も厚い法律家です。
今回、社協からの依頼によって、身寄りのない高齢男性の後見人を担うことになりました。その男性は、認知症を患い、徘徊のリスクが極めて高い状況にありました。さらに、経済的にも困窮していたため、Xさんは生活保護の窓口である福祉事務所に支援を求めました。
その際、福祉事務所の担当者からは「生活保護の申請と施設入所をセットで進めましょう」との提案があり、引っ越し費用も保護費から支給されるとの説明を受けました。Xさんは、その言葉を信じて、高齢男性の意思も確認のうえ、認知症グループホームへの入所の手続きを進め、無事に男性は施設に入所することができました。生活保護の申請も受理され、あとは引っ越し費用の精算を残すのみとなりました。
ところが、その引っ越し費用を請求したところ、福祉事務所から返ってきたのは「出せない」という言葉でした。
Xさんが理由を尋ねると、「引っ越しの時点ですでにグループホームに入所していたから。入所前でなければ引っ越し代は出せない」との説明。最初に「引っ越し費用は出る」と聞かされていたと抗議すると、「そんな話はしていない」、「相談せずに勝手に引っ越しを進めたのが悪い」と突き放されました。
成年後見人は、法律に基づいて本人を保護し、支援する立場にあります。本人の命と安全を第一に考え、速やかに入所手続きを進めたのは当然の判断でした。その過程で、行政の提案に従い、指示に基づいて動いたにもかかわらず、あとになって手のひらを返されたような対応を受けたのです。
認知症グループホームに入所しながら生活保護を利用するということは、生活保護費のほとんどが入所代に費やされてしまい、手元に残るお金はないに等しいのです。実際にグループホームの職員に尋ねてみたのですが、「洋服を買ったり、ほかの利用者さんと同じように外食したりするので、手元に残るお金はほとんどない」そうです。
Xさんは、「引っ越し屋さんには分納で支払うしかないか・・・」と肩を落としていました。しかし、分納できるほどのお金が残るかどうかわかりません。
* * * * *
今回の一件は、地域で高齢者を支えるすべての福祉関係者にとって、他人事ではないはずです。誤解を招く説明、責任のすり替え、そして柔軟性のない運用が、結果として現場の信頼を損なっています。
本来、福祉は「困っている人の味方」であるべきです。支援を求める人に対して、「説明が足りなかった」ことを棚に上げ、「勝手にやったのが悪い」と責める姿勢は、本来の役割から外れています。
このような対応が繰り返されれば、安心して相談できる環境は崩れてしまいます。私たちは声をあげるべきです。「制度の穴」に泣かされる人がこれ以上出ないように、現場の声を政策に反映させる努力が必要です。