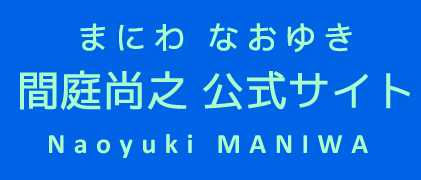〔前回までの内容〕
群馬県桐生市の生活保護行政がヒドい! 申請者への暴言・恫喝、申請させないような違法行為。ケースワーカー(生活保護の担当者)が「1日千円で生活しろ!」と生活保護受給者に強要していた・・・今年度から江東区でも生活保護を受給している人への金銭管理の事業が始まります。大丈夫なの?!
じつは、福祉サービスの中でも金銭管理の分野があります。基本的にそれは「本人の意思を尊重」して慎重に執り行われるものです。さもないと財産権の侵害となってしまうからです。金銭管理事業は、その慎重さゆえに使いづらいサービスとなっています。しかし、判断能力が低下した人にとっては、なくてはならない事業です。
〔まず桐生市〕
3月28日にとうとう桐生市の市長が「利用者に耐えがたい苦痛や不利益を与えた」と謝罪をすることになりました。当然です! 桐生市では10年で生活保護利用者が半減したんです。異常事態だと思わなかったのでしょうか。第三者委員会の調査ではさまざまな違法行為が指摘されています。
〔さて、金銭管理の事業〕
まずはちゃんとおさえておきたいのは、「お金があると浪費しちゃうので強制的に金銭管理する」ではない!ということです。金銭を管理してもらいたい意思がある人に対する支援です。繰り返しになりますが強制的な管理ではありません。
金銭管理の福祉サービスとして、市区町村社協が「日常生活自立支援事業」を実施しています。ただ、使い勝手がよくありません。だから、社協の事業だけでなく、生活保護利用者にフォーカスした「被保護者金銭管理支援事業」という事業もあります(役所が支援団体に委託して実施)。生活保護の利用者はどっちの事業を使ってもいいんです。東京東部に関していえば、後者の事業は、墨田区などではすでに実施されています。江東区は本年度から開始です。
〔ケースワーカーの支援でいいのか〕
ここからは、生活保護の支援の仕事について書いていきます。生活保護を受給すると、受給者には「ケースワーカー」(「生保ワーカー」ともいう)という役所の担当者がつけられます。ケースワーカーの役割は、社会福祉法で「本人(生活保護受給者)に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる」と規定されています。支援ではなく、「指導」ですからかなりキツい響きではあります。桐生市のように指導の権限を濫用する危険性もあるのですが、ほとんどの職員はまじめに職務に専念しています。
〔現状がいびつ〕
ひとりのケースワーカーが生活保護利用者の生活全般を指導するというのはいかがなものでしょう。私はこのようなやり方は本来的に社会福祉にそぐわないと思っています。というのも、福祉的支援というのは、チームで実施されるものだからです。チームは多くの支援者で編成されています。
ひとりの人間に支援の権限を集中させると、だいたいの場合、支援者がエラそうになります。また、共依存的な関係になることもあります。いわゆる属人的な支援になりがちなのです。そうならないようにケースワーカーの異動サイクルは早くなっています。いずれにしても対人支援の基本はチームなのにケースワーカーひとりに任せている現状がいびつな形なのです。
「チーム支援が素晴らしい」と個人的な印象で話しているわけではありません。多くの支援者が関わっているほうが効果的であるという研究がかなり前からあります。複数人で手分けをして支援することは、ソーシャルワークの常識なのです。
「属人的支援(個人に依存する支援)」よりも「多職種協働・多機関連携(チームによる支援)」のほうが、サービス利用者の健康・福祉の向上、サービスの質の向上、職員のバーンアウトの軽減などに寄与するのです。そのようなエビデンスは多数あります。ちょっとググってみてください。
〔利用者にもやさしい〕
一般的に考えて、コロコロ異動してしまうひとりの役人よりも、多くの関係者が安定的に関わってくれる方がいいに決まっています。また熊谷晋一郎さんの言葉を借りれば、「自立とは、依存先を増やすこと」なのです。チーム支援こそ、拠り所を増やす、自立とエンパワメントに向けた取り組みです。
チーム支援だと「責任が分散して、かえって無責任」という批判があります。こんなこと言う人に限って、ちゃんとしたサービス関係者会議をやっていない。本人を交えた関係者会議で役割分担と責任の所在を明確化するのが多職種連携です。
そういえば、私はケースワーカーが主催する関係者会議に出たことがないですね。どうせ「法定業務ではないから」という理由でやらないんでしょうね。本来は、ケースワーカーこそ生活保護の統括責任者として連携を進めるべきなのに!
〔ケースワーカーもたいへん〕
そうはいっても現状、ケースワーカーの業務量は膨大です。ワーカーひとりあたり基本マックス80件を担当します。100件を超えたケースを担当させられる自治体もあります。訪問調査、毎月の保護費の確認など業務負担はかなりのものです。
そして、ケースワーカーは「現金を扱っちゃダメ」と規定されています。たとえば、生活保護費をすぐにつかってしまう人がいるとします。その人に保護費を小分けにして現金で渡すこと・・・これも厳密にはNGなんです。
保護費は毎月月初に銀行振り込みで支給されます。たしかに現金管理は事故につながりやすいということはあります。しかし、生活保護費を支給する担当者が現金を扱えないとはいかなることでしょう。果たして業務として成立するのでしょうか。
〔よりよき支援に向けて〕
見てきた通り、金銭管理を別の支援主体が担うというのは3つの意味でいいことなのです。つまり、①チーム支援になる ②利用者に資する ③ケースワーカーの負担軽減になる。
生活保護での金銭管理支援において重要なのは、ケースワーカーが支援全体の統括者である立場をきちんと自覚して仕事していることです。「金銭管理は、別の支援者に任せたからオレは知らないよ」では通りません。役割を丸投げするのではなく、支援の進行管理を務める責任が役所にはあります。
また、金銭管理事業を受託した団体も時間がかかって使い勝手がわるいという批判に耐えながら、利用者の意思を尊重した慎重な支援をしなければなりません。桐生市のように利用者の意思を無視して「1日千円生活」など許されることではありません。
〔大きくまとめ〕
たいそう大きい話で締めくくります。社会保障は、「社会福祉」・「社会保険」・「公的扶助(生活保護)」・「公衆衛生、保健医療」の4つの分野から構成されます。これは独立してタテワリで動いているわけではありません。連携・協働してこそ社会保障として力を発揮します。生活保護や介護保険は国法が根拠規定だから地方行政は判断できないなんて言って、連携を拒んでいるようじゃダメなんすよ。多くの支援者が手分けしてチームとして関わっていき、市民が拠り所を多くもつことが理想的な社会保障の姿です。