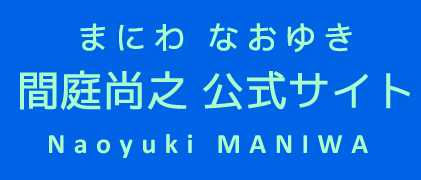これは、2024年8月5日に投稿した「意思決定支援の普及に向けて」の加筆・修正版です。いろいろあって加筆・修正することになりました。今回のほうが具体例が盛り込まれ、よりわかりやすくなっているのでぜひご一読を。
〔新聞記事~スウェーデンの認知症ケア〕
下記のものは、先日、ヨミドクター(読売新聞の医療介護情報サイト)で読んだ記事のおおまかな内容です。
「スウェーデンでは、認知症ケアにおいて、自己責任の考えがあるからよいケアが可能となる。命の危険があったとしても自己決定には自己責任が伴うので、本人の希望が尊重されるべき」。
要するに認知症を患った状態でも自分で決めたことなのだから「リスクは自分で負いなさいよ」という理屈です。ほんとうにそれでよいのでしょうか。そもそもスウェーデンの認知症ケアは、自己責任論が背景にあるのでしょうか。
〔認知症は、自己責任か〕
私の結論として認知症に自己責任論を適用するのは誤りです。認知症の人が命の危険が伴うような行動や決定をして、それを支援者が放置してしまったらネグレクト(介護放棄)と同じです。
「終末期医療」と「認知症の人の介護」が混同されているのかもしれません。ターミナルケアと認知症ケアは、その対応がかなり異なります。
ターミナルケアでは患者自身が望む終末期医療を行うこと(延命治療をするかどうかなど)が一般的なので、ある意味、自己責任が適用される場面ともいえます。
一方で、認知症ケアでは、患者本人の判断能力の低下が伴います。自分に不利益な自己決定をすることがあります。また、認知症の人の決定の裏には、別の問題が潜んでいることもあります。
たとえば、中重程度の認知症の人が食事をとることを拒否したとしましょう。これを高齢による食欲の減退として、食べない決定を尊重し、低栄養での衰弱を仕方がないものとみなすことがあったとします。
当然ながら、認知症の人は自分の状況を説明できません。とすると、秘められている認知症の人の心身状況の可能性として、いろいろなことが考えられます。口腔内に異常があり、食事がとれないのかもしれません。便秘で食欲がなくなっているのかもしれません。はたまた、なじみの職員がいなくなって不安が募っていて、食欲がなくなっているのかもしれません。要するに食事を拒んでいるからといって、高齢による食欲の減退と簡単に決めつけるのは認知症の人の支援においては早計なのです。
認知症のケアに自己決定論を適用することは、荒っぽい支援であると思います。自分にとってのリスクがどういったことか、わからなくなってしまうのが認知症であり、それが判断能力の低下ということです。相応の支援をしなければなりません。
〔意思決定支援〕
認知症支援に自己責任論を持ち込んでしまうのは、これまでのソーシャルワークの議論をフォローしていない証拠です。社会福祉士・精神保健福祉士の間では、判断能力が低下した人のケアに関して、「意思決定支援」や「権利擁護」という概念が普及しています。
意思決定支援とは、英語でsupported decision-making、つまり「支援を得た意思決定」。どんなに重度の認知症の方でも絶対に意思があるということを前提にした支援の手法です。そして、判断能力が低下した人を支援するしくみ全般を「権利擁護」と呼んでいます。
意思決定支援は、障害者権利条約や成年後見制度の文脈でよく語られます。いま成年後見制度の見直しの議論が進行しています。2024年の4月から成年後見に係る法制審議会が開かれています。その中で、家族のためではなく、認知症を患った当の本人に資する制度に向けて、意思決定支援の普及・推進が議論されています。
日本の認知症ケアは、本人の意思を無視した「代行決定(substituted decision-making)」といわれ、国連から非難されています。意思決定支援において、代行決定は最後の手段です。
スウェーデンの認知症ケアが突出して優れているわけではなく、先進国における権利擁護のスタンダードが意思決定支援なのです。
〔本人意思と家族(第三者)の意思〕
ヨミドクターの記事は、日本において家族の決定が本人の決定になってしまうことへの懸念を示していて、それゆえの自己責任論を採用するという流れでした。
確かに、日本の福祉支援では、家族の思いのほうが本人の意思よりも重視されてしまうことがあります。これは非常に問題です。
少なくとも現行のまともなソーシャルワーク教育を受けている人であれば、家族の意向は「関係性への配慮」として受けとめられます。つまり、関係者の参考意見とみなされるというわけです。あくまで本人の意思を尊重しなければならないとされています。とはいえ、支援者でもなかなかこのことを理解してない人が多い。
先日、福祉関係者と話していたら「家族の意向だから仕方がない」、「本人の意に反してもリハビリさせる」という言葉を聞きました。さらに「利用者を施設入所させるための担当者会議をしましょう」なんてこともありました。入所するかどうかは利用者が決めることなのに・・・。いまだにこんな発言が出る時点で残念です。
〔本人の意思の尊重をめぐって〕
まっとうな福祉専門職であれば、福祉的支援は、家族の意思ではなく、「本人の意思」を尊重することであると理解しています。本人の意思と家族の希望が対立する場合にそれを(ここが重要!)「本人の立場に立って」調整するのがソーシャルワーカーの役割です。
安易な自己責任論を採用すると利用者に対して「あなたが決めたことなんだから、どうなっても知りませんよ」とか「あなたの希望では支援者が責任をもって支援することはできません」など、支援者側の開き直りに流れるでしょう。
これとは逆に家族や支援関係者が介護で疲労困憊しているのに、利用者のことにフォーカスしすぎて、「(利用者)本人は困っていません。家族が困っているだけです」といって周辺に配慮をしない支援者もいます。
これもNGです。意図的ではないにせよ、利用者の決定がほかの人の生活を損なってしまうことがあります。これには何らかの対応を要します。ただ、認知症などの利用者は、判断能力が低下しているがゆえに適切な決定ができないことに注意する必要があります。
たとえば、妻以外の人物から介護されることを拒否する認知症の夫がいるとします。高齢の妻は夫の介護が非常に負担で「死にたい」とケアマネジャーに話している・・・判断能力の低下した夫は、妻に介護する体力がないことを理解できていないのかもしれません。こういった場合、夫の希望をそのまま尊重するというわけにはいきません。成年後見人などが介入した支援などさまざまな方策を検討することになるでしょう。
〔意思決定支援の法整備を〕
厚労省からさまざまな意思決定支援ガイドラインが出ています。しかし、残念だと思うのは、意思決定支援が法制度として導入されていない点です。
また、やや毛色が違いますが、厚労省は、ACP(advance care planning・人生会議)の推進もしています。意思決定能力のあるうちに自分自身の将来の医療についての計画を立てておくことです。
こういった議論は、きちんと制度化されていません。それが意思決定支援があまり普及していない原因でしょう。現状では、認知症の人の意思をどう扱うか、どう支援するかに関して、十分に検討されていない勝手な議論が横行しています。それが支援者間での混乱を招いています。
* * * * * *
いずれにしても認知症の人に自己責任論を適用しようなんて夢にも思いませんでした。そんな浅はかな支援で判断能力が低下した人が幸せになるとでも思っているのでしょうか。ヤレヤレといったところです。