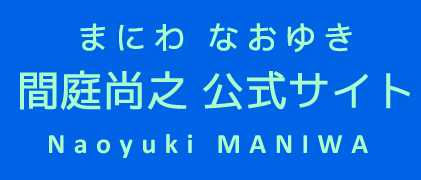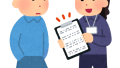先日、医療ソーシャルワーカー(MSW)の方々とグループ討議をする機会がありました。テーマは「身元保証人」。私たちが医療機関に入院したり、施設に入所したりする際に求められる身元保証人の存在は、現場で長く議論されてきました。私がいつも言っているのは、これは単なる病院と個人の契約の問題ではなく、本質的に「権利擁護の問題」ということです。
「身元保証人がいないと、この人は受け入れられない」、「保証人がいないから入院の調整が進まない」・・・こうした現場の声は珍しくありません。恐ろしいことに、そこで制限されているのは、実は権利そのものなのです。身元保証人がいないというだけで必要な医療が受けられない、安心して暮らせる場所に移れない、これは制度の不備や社会構造の問題であり、本人の責任ではないはずです。
討議の中で、あるMSWがこう語りました。「権利を主張する前に、患者さん本人が経済的な義務を果たしてほしい」。もちろん経済的負担の現実は理解できます。ただ、この発言は誰の立場を代弁しているのでしょうか。ソーシャルワーカーは本来、組織ではなくクライアントの利益を代弁する専門職のはず。にもかかわらず、経済的リスク管理を優先してしまうと、いつの間にかクライアントの声が組織の論理に置き換わってしまいます。
釈迦に説法を承知で言いますと、権利と義務はセットではありません。人は誰しも弱い存在です。常に先々の経済的リスクまで見通して行動できるほど計算高くないですし、将来の義務が発生する可能性を完璧に理解しながら生きている人などいません。むしろ「弱さ」を前提とした支援こそが、ソーシャルワークの原点だったはず。困難を抱える人に寄り添い、支えていくことへの想像力を欠いた支援は、もはや支援ではありません。
もちろん経済的な側面は無視できないですよ。でもそれは本人に負わせるべき義務ではなく、本来、社会が担うべき責任です。日本の社会保障制度は、弱い立場の市民を守るためにあります。身元保証人がいないだけで排除されたり、経済的リスクを背負わせたりするのは、制度が本来果たすべき役割を放棄している状態です。
こうした問題のなかで、身元保証会社(高齢者等終身サポート事業者)を安易にすすめる流れが強まっています。しかし、こちらも慎重であるべきです。利用者の弱さにつけ込む悪質な事例も少なくありません。
ソーシャルワーカーの立場はいつも難しい。病院という組織に属すれば、どうしても組織の利益やリスク管理が優先されます。働いていて、知らず知らずのうちに組織の論理で考えるようになり、地域と社会をつくり変える視点(コミュニティワークやソーシャルアクション)が薄れていきます。
本来のソーシャルワークはもっと広い視野を持っています。個人の問題を社会の問題として捉え、制度の不備や不公正を是正する立場です。
みんな! 「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(知らない人はググってね)に立ち戻るんだ!
私たちソーシャルワーカーは、「身元保証人の必要性」を問うのではなく、「保証人がいないからといって生きる権利が奪われていいのか」と社会に訴えねばならないのです。
ちなみに「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」は以下です。
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。