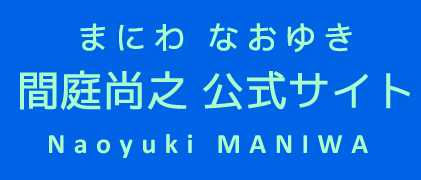わけのわからないカタカナの題名でスミマセン。今回は、新自由主義に対抗するために「コモン(公共財・共有資源)」の領域を拡大しようとする動きとその評価のお話です。
「市場原理こそが最適な資源配分を実現する」というご存じの新自由主義の考えがあります。新自由主義が主張する市場原理が公共の領域にまで持ち込まれ、インフラや福祉、医療、教育など、誰もが平等に受けられるはずのサービスが民間企業によって運営されるようになっているわけです。そして、平等にあるべきサービスが一部の人、要するに富裕層に集中する事態が起きています。
上下水道、公共交通、医療、保育、さらには公営住宅に至るまで「民間のほうが効率的」という名目のもとに民営化が進められてきました。こうした動きが結果として何をもたらしたかといえば、効率化と引き換えにした排除と格差の拡大です。たとえば、水道料金が跳ね上がった自治体や、採算が取れない地域から撤退する地域公共交通事業など、サービスの質や公平性が著しく損なわれる例が各地で報告されています。
こうした中で「コモンの領域を増やす」、つまり、再公営化や民営化の阻止を目指す運動が活発化していることは、行き過ぎた新自由主義に歯止めをかける、とても健全な動きであると考えます。
とはいうものの、コモンを拡大することで問題になってしまうことがあります。すなわち、その運営の在り方です。多くの人が懸念するのが、いわゆる「お役所仕事」。非効率さや硬直性が公共サービスにはつきものです。民間企業のような迅速な意思決定や柔軟な対応が行政には乏しく、利用者目線のサービスが行き届かないといった現実が間違いなくあります。
私自身かつて、都立病院の独立行政法人化に反対の気持ちでした。しかし、実際に法人化された後、職員の意識改革や経営改善が進み、サービスの質が向上したという事実を多く耳にしています。また、先日、大手スーパーの人事担当者と話をする機会があったのですが役所の正規職員採用が年1回だけという非効率さに驚いていました。
こうしたことを鑑みるに「コモンか、民間か」という二項対立ではなく、より大切なのは「市民のために真に機能する仕組みとは何か」という視点です。コモンの拡大は、市民の権利の保障という点で重要ですが、それがお役所仕事によるサービス低下だとしたら本末転倒です。
だからこそ、コモンの拡大には、必ず役所組織のガバナンス(運営管理)の強化と見直しが伴わなければならないと思います。
公共サービスのガバナンスとは、教科書的に言うと「行政の説明責任の徹底」、「第三者評価の仕組み」、「市民参加型の運営体制の導入」、「現場の声を吸い上げる柔軟な制度設計」などが挙げられます。しかし、現実的にこれらを実行できるのでしょうか。
これまでお堅い話をしてきましたが、まずは、役所文化をどうにかしなきゃ。生活保護の申請をする人を追い返してしまうような組織にコモンを任せられますか、ってことです。日本の役所は、ホントにコモンを担えるのでしょうか。役所の体質を変えない限り、本当の意味でのコモンは実現しません。