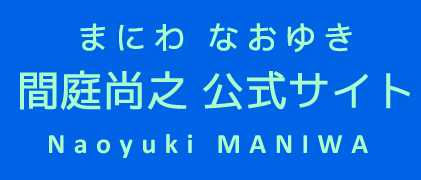今回は、めずらしく教育の話題です。
私は教育の専門家ではありませんが、学校は「こどもの可能性をひろげる場所」であるべきだと考えています。近年、職業訓練的な授業や金融教育などを重視する動きも見られます。もちろん、社会に出てから役立つ知識やスキルを身につけることは大切です。しかし、それらが学校教育の一部に据えられることには違和感を覚えます。こどもの時期にしかできない体験や学びが、なおざりにされてしまうことを心配しています。
先日、ある福祉関係者の集まりで、こどもの支援について議論する機会がありました。その席で、「江東区にはこども用のインキュベーションセンターがないのが最大の問題だ」と語る参加者がいました。つまり、起業を志すこどもたちを支援する拠点が必要だというのです(ちなみに私は「インキュベーションセンター」の意味を知らなかった!)。驚いたことに、その意見に賛同する福祉関係者も少なくありませんでした。まあ、たしかに、起業に関心を持つこどもがいても不思議ではありません。その選択肢もアリです。とはいえ、私はとても違和感を覚えました。
いまのこどもたちは、受験や成果主義的な評価に追われています。そんな中で、さらに「経済的自立」や「ビジネスマインド」を早くから求めるような風潮に関しては、ちょっとどうかと思います。
こどもの時期は、人生の中でいちばん自由に「寄り道」ができる時間があります。スポーツに打ち込むこと、音楽や絵を通して感性を育むこと、友達との関係を通して人を思いやること・・・そんなカッチョいいことだけでなく、人や社会に迷惑をかけない限り、ひきこもっていたって、ヤンキーになっていたっていいと思います。寄り道はこどもの特権です。それらの時間はすべて、将来、大人になってからのその人の魅力になります。
ビジネスは大人になってからでも、いくらでも挑戦できるわけです。大人は「短期的な結果を出す=金持ち」という思考で、こどもの寄り道が時間のムダに見えるのかもしれません。しかし、寄り道は、こども時代にしかできない重要な活動です。大人になってからの寄り道はハイリスクですからね。
役に立たないムダなことに見えても、いいじゃないですか。大人の私たちができるのは、子どもたちが安心してムダな時間を過ごせ、失敗できる環境を整え、安全に寄り道できるように見守ることだと考えます。こどもが自分のやりたいことに夢中になれる時間を大切にしたいですネ。
* * * * *
話変わって、最近、ICT教育について、極端な議論が目立ちます。デジタル技術の活用を「遅れたら取り残される」と過度にあおる動きがある一方で、「タブレット学習など不要! 手書きこそ本物」といった意見もあります。私はどちらにも同調できません。
強調したいのは、ICT技術は、こどもが将来の社会で必要な感覚を身につけるうえで欠かせない一方、それ自体は教育の目的ではないということです。ICTは、はさみやペンといった文房具のひとつです。デジタルとアナログ(フィジカル?)の2項対立ではなく、使いやすい方、効果的な方を自由に選べばいいと思います。デジタルもアナログも両方とも大切です。